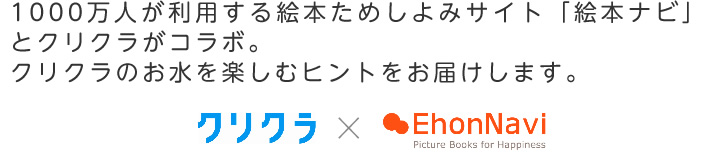初夏から要注意!今から夏まで親子みんなで熱中症対策

5月から6月は気温も上昇するため、熱中症に注意が必要な時期。毎年約5万人が救急搬送されているという熱中症について、日本気象協会に聞いてみました。これから夏に向けて大人も子どもも安全に過ごすために知っておきたい予防法と対策をご紹介します。
一般財団法人
日本気象協会
1950年の設立以来60年以上にわたり、生活に身近な気象情報や天気予報を発表している、国内最大規模の民間気象団体です。
熱中症にかかる方を減らし、亡くなってしまう方をゼロにすることを目指すプロジェクトも行っており、発生に大きな影響を与える気象情報の発信を中心に、積極的な予防や対策を呼びかけています。

日本気象協会に聞きました!
― 大人も子どもも知っておきたい熱中症Q&A ―

Q. 熱中症ってどんな症状?
A. 熱中症は、高温多湿な環境に、私たちの身体が適応できないことで生じるさまざまな症状の総称です。
軽度の場合は、めまいや顔のほてり、筋肉痛や筋肉のけいれんを感じることがあります。体のだるさや吐き気や頭痛がしたときには注意が必要。
最終的には呼びかけに反応できないなどの状態になってしまうこともあります。反応がなかったり、まっすぐ歩けないなどの異常があるときはすぐ医療機関を受診してください。
Q. 熱中症に気をつける時期とは?
A. 熱中症に特に気をつけてほしいのは、5月の暑い時期・梅雨の晴れ間・梅雨明けからの盛夏・お盆休みとお盆明けです。
真夏だけではなく、気温が急に上がりはじめる5月から気をつけましょう。
Q. 特に気をつけたほうがいいのはどんな人?

A. 乳幼児や子ども、高齢者、屋外で働く人やキッチンで火を使う人、スポーツをする人は特に注意が必要です。
乳幼児や子どもは自力で移動することができないので、「寝ているから」「ちょっとの時間だから」と暑い場所に放置することは危険です。特に、車内に置き去りにすることは絶対にやめてください。
高齢者の方は温度に対する感覚が弱くなるため、室内でも熱中症にかかりやすいといわれています。入浴時や就寝中にも体の水分は失われているため、気づかないうちに熱中症にかかってしまうことがあります。入浴前後に十分な水分補給をしたり、寝るときは枕元に飲料を置いたりするのがおすすめです。
暑い日にキッチンで火を使う人も注意が必要です。調理中も体を適度に冷やせるネックバンドや冷やしたタオルを利用するといいですね。また調理中は換気扇を回すことも忘れずに。
― 熱中症予防&対策 ―
●毎日の生活で気をつけること
食事をしっかりとる
丈夫な体作りは熱中症対策の基本。バランスのよい食事をとるだけでなく、しっかりとした睡眠や適度な運動を心がけましょう。
気温と湿度をいつも気にする
自分のいる環境の気温や湿度をいつも気にすることが大切。温度が低くても湿度が高いと熱中症にかかるリスクが高くなります。屋内の場合は、日差しを遮ったり風通しを良くすることで、気温や湿度が高くなるのを防ぎましょう。
水分をこまめにとる
のどがかわいていなくても、こまめに水分の補給を。スポーツドリンクなどの塩分や糖分を含む飲料は水分の吸収がスムーズにでき、汗で失われた塩分の補給にもつながります。
※ただし、かかりつけ医から水分や塩分の制限をされている場合は、よく相談の上、その指示に従ってください。

●外出のときに気をつけること
飲み物を持ち歩く
水筒などでいつも飲み物を持ち歩き、気づいたときにすぐ水分補給するのを習慣に。
衣服を工夫
衣服は麻や綿など通気性のよい生地を選んだり、下着には吸水性や速乾性にすぐれた素材を選ぶとよいです。また汗で濡れた服は、体内の熱をこもりやすくするのでこまめに着替えましょう。
日よけグッズや冷却グッズを活用
帽子や日傘で直射日光をよけたり、なるべく日かげを選んで歩いたり活動したりするようにします。そのほか、冷却シートやスカーフ、氷枕などの冷却グッズを利用しましょう。首元など太い血管が体の表面近くを通っているところを冷やすと、効率よく体を冷やすことができます。
休憩をこまめに
暑さや日差しにさらされる環境で活動をするときなどは、こまめな休憩をとり、無理をしないのがポイントです。
●室内にいるときに気をつけること
室内を涼しく
扇風機やエアコンで室温を適度に下げます。過度の節電や「この程度の暑さなら大丈夫」とガマンするのは禁物です。
睡眠環境を快適に保つ
通気性や吸水性の良い寝具をつかったり、エアコンや扇風機を適度に使って睡眠環境を整え、寝ている間の熱中症を防ぎます。同時に、日々ぐっすりと眠ることで翌日の熱中症を予防しましょう。
― 熱中症の応急処置で大切な
3つのポイント ―
・めまいや顔のほてり
・筋肉痛や筋肉のけいれん
・体のだるさや吐き気、おう吐
・汗のかきかたがおかしい
・体温が高い、皮ふの異常
上記のようなサインがあったときはすぐに応急処置を行い、改善が見られない場合は、病院などの医療機関へ。 また、呼びかけに反応しない、まっすぐに歩けない、水分補給ができないなどの場合は、重度の熱中症の可能性がありますので、すぐに119番へ連絡し、救急車を呼んでください。救急車を待っているあいだにも応急処置をすることで、症状の悪化を防ぐことができます。

ポイント1 涼しい場所へ移動
まずはクーラーが効いた室内や車内へ。屋外で、近くにそのような場所がない場合には、風通りのよい日かげに移動し安静にします。
ポイント2 衣服を脱がし、体を冷やして体温を下げる
衣服をゆるめて、体の熱を放出。氷枕や保冷剤で両側の首筋やわき、足の付け根などを冷やします。皮ふに水をかけて、うちわや扇子などであおぐことも効果的。
ポイント3 塩分や水分を補給
できれば水分と塩分を同時に補給できる、スポーツドリンクなどを。おう吐の症状が出ていたり意識がない場合は、誤って水分が気道に入る危険性があるので、無理やり水分を飲ませることはやめましょう。

防ごう、脱水!
熱中症に負けない食生活のポイント
― 管理栄養士さんに聞きました―
●体重1kgあたり、成人は50ml、子どもは100mlの水分が必要 (※)
熱中症による心配のひとつが脱水症状。成人は体重1kgあたり50mlの水分を必要なのに対し、子どもは体重1kgあたりその倍量の100mlの水分を必要とすると言われています。また高齢者は、腎機能の低下などにより暑い日には特に脱水症を起こしやすくなるため、こまめな水分補給が重要です。
※飲料として飲む水分量のほかに、食事などから摂取する水分も含んだ、1日に必要な水分量です。1日に必要な水分量の半分は、食事などから摂取しているといわれています。
●脱水予防に効果的な水分とは?
重要なのは、利尿作用のあるカフェインを含まないこと。
そこでおすすめなのが麦茶です。麦茶はカフェインを含まず、汗として奪われるミネラルも豊富に含まれています。水に入れるだけのパックタイプのものなど販売されているので、気軽に取り入れられますね。
「熱中症には塩分」という話を耳にしたことがあるかもしれませんが、1日のほとんどをエアコンのきいた室内で過ごす場合は、食事からとる塩分で十分。
しかし、屋外でたくさん汗をかく場合には、水分だけでなく、汗によって失われる塩分をとるよう心がけましょう。
水500mlに塩小さじ1/6、はちみつ大さじ2 、レモン汁小さじ1を加えた手作りドリンクがおすすめです。はちみつとレモンには疲労回復の効果も期待できますよ。

※1歳未満の子どもには、はちみつは与えないでください。
※はちみつを砂糖大さじ1に代えても作れます。
※高血圧、心臓病、腎臓病などで通院している人は医師に相談してください。
●日頃の食事で熱中症予防
熱中症は疲れが溜まっている時に起こりやすいと言われています。
食事では、疲労回復効果のあるビタミンB群を含む豚肉、大豆等の豆類(豆腐・豆乳・納豆など加工食品もOK)、アリシンを含むにんにくなどを積極的にとりいれてみましょう。

尾花友理さん
管理栄養士、フードコーディネーター
給食委託会社において産業給食、保育園給食などの献立作成及び給食管理、栄養相談など経験したのち、料理研究家のアシスタントとしてレシピ開発、料理講師、テレビや書籍の撮影アシスタントなどとして活動。その後、レシピサイト運営会社において管理栄養士として調理や食の安全に関す業務などに従事後、独立。
●体うるおす水、心をうるおす絵本
青空の下にそよぐ新緑を眺めていると、これから迎える季節にふと思いをはせること、ありませんか。 1本の木をめぐる1年の物語を、ご紹介します。
いろいろ1ねん
- 作・絵: レオ・レオニ
- 訳: 谷川 俊太郎
- 出版社: あすなろ書房
一本の木とふたごの子ネズミがともに過ごす一年間。
訪れる季節の変化とそこで育まれる温かな友情を描いた
レオ・レオニ後期の名作絵本です。